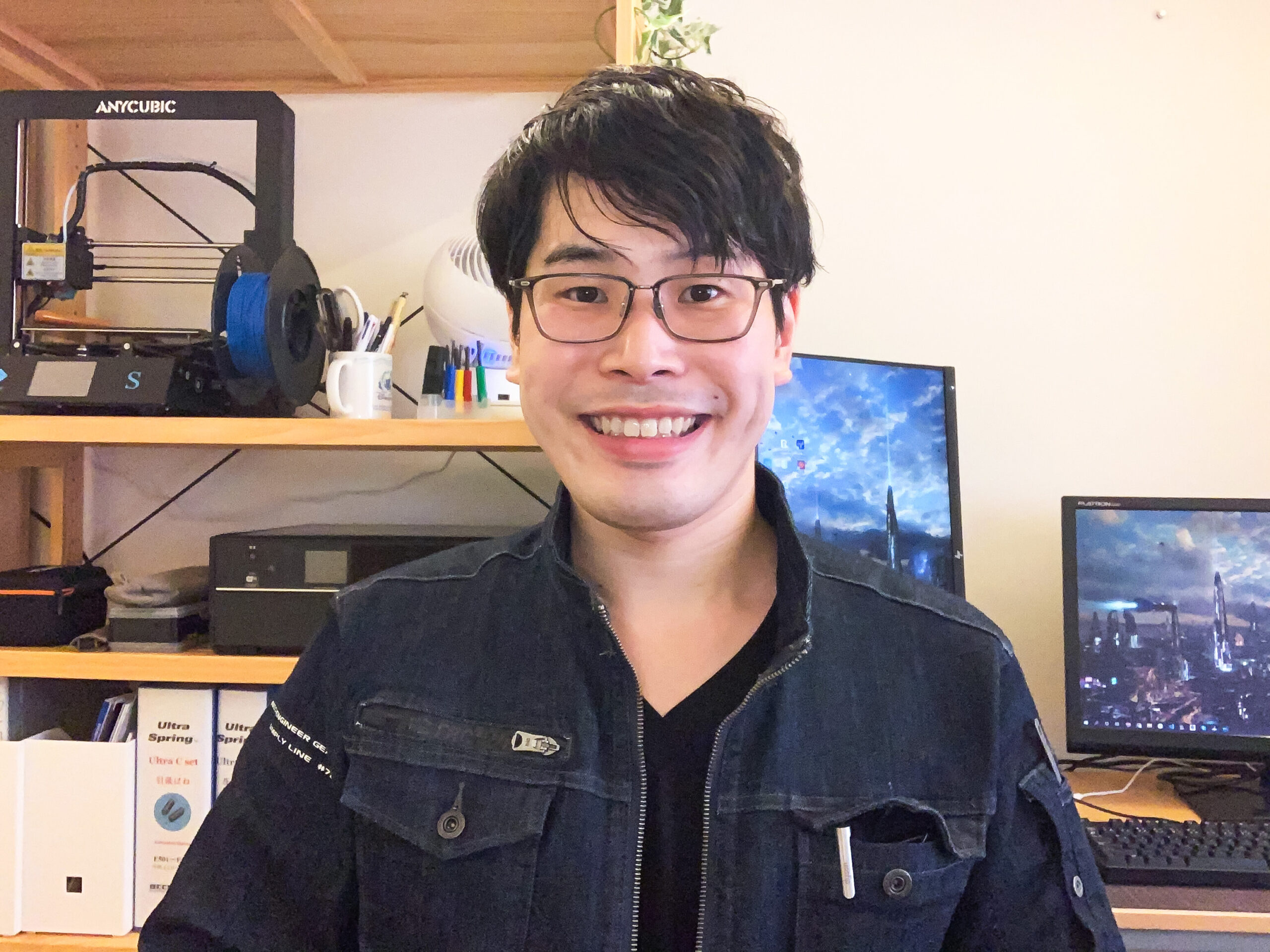こんにちはー、りびぃです。
普段は生産設備の設計をしている現役エンジニアです。
私は普段FA(ファクトリー・オートメーション)の業界でものづくりに携わっており、単に設計をするだけではなく実際の現場に出向いて仕事をすることもしばしばあります。
こういったプロジェクトの一連の工程を担当しているとどうしても「あぁ、ここ失敗したなー」「またその件でミスが発生したなー」という失敗やミスに気づいたり、発生したりします。
この中にはものづくり業界では「あるある」なものも多いのですが、それらを分析すると、主に3つのHに分類されるケースがほとんどだと言われています。
その3つとは、
- 初めて (Hajimete)
- 変更 (Henkou)
- 久しぶり (Hisashiburi)
です。
この失敗の3Hは設計者のような事務所作業だけではなく、現場作業者においてもとても良く当てはまるミスの経験則でもあります。
失敗の一つ一つは小さなものかもしれませんが、そのような積み重ねが大きな失敗や事故を引き起こす引き金になってしまうというのは「ハインリッヒの1:29:300の法則」として非常に有名です。
ですからこの3Hについて学ぶことは、ものづくり業界で働くみなさんにとっては間違いなく重要であると言っても過言ではありません。
そこで今回はこの失敗の3Hとはなにか、どのように対策をすればよいかについて、事例を交えながらわかりやすく解説をしていきます。
よく起こる失敗その1:初めて

- 初めての取引先との仕事
- 初めての品種の製造自動化プロジェクト
- 初めていく現場での作業
などのように「初めて」のことが絡むものは失敗が起こりやすいものの一つです。
初めてのことは失敗が起こりやすい原因についていくつかご紹介していきます。
1つ目は「勘所がわからないから」です。
機械設計で言えば、例えばワークの圧入装置を設計したことがない人が圧入装置を設計しようとすると、どういった点の考慮が必要かがわからないまま想像で設計することになります。
実際圧入装置を設計する上では、
- 圧入のパンチとダイの組立精度をどの程度合わせておく必要があるのか
- 圧入前に装置に対するワークの位置決めをどのようにして行うのか
- 圧入荷重をどのようにしてコントロールするのか
- 強度の低い部品に圧入時の衝撃荷重がかからないために、どのような工夫が必要か
などを考える必要があり、この設計によって圧入された製品の品質が大きく左右されます。
2つ目は「正しい作業手順、効率の良い作業方法がわからないから」です。
例えば初めて担当する機械を組み立てる中で、
- 工具アクセスが非常に悪いため、A部とB部との組立順を逆でするべきだった>
- 測定をしながら組み立てないといけない箇所が多いため、事前に治具を製作しておくべきだった
- C部の組立は複数人でやらないとうまくできないため、事前に作業者同士のスケジュール調整が必要だった
- a部品とb部品は、形状は似ているが違う部品だということが組立後にわかり、再組立てをしなければならなくなった
- エンドユーザから支給されるワークや部品がないと組立調整できない箇所があるため、早い段階で支給要請をしておくべきだった
という問題はしばしば起こります。
3つ目は「心理的なプレッシャーがあるから」です。
生産設備のプロジェクトは「おそらくこれぐらいの時間で終わるだろう」「おそらくこれぐらいの予算が必要だろう」などという想定をベースに進められるケースがほとんどです。
ですが初めてのものとなると「本当にその想定通りに進むのか」が全く見えないまま作業をしていくという状況になります。
「初めてのものはトラブルがつきものだから」という想定で、ある程度スケジュールや予算に余裕を持たせておくことをしたとしても、実際はさらにそれ以上に時間やコストがかかってしまったということは、本当によくあることです。
それによってプロジェクト関係者間に「焦りや緊張感」の空気が漂い始め、それがさらに次のミスを誘発することもよくあります。
「初めて」に起因する失敗への対処法
とはいっても、誰でも最初は「初めて」を必ず経験するものですから、一切の失敗をすることなくいきなりプロジェクトを完璧に遂行できることはあり得ません。
ですが、少しでも失敗のリスクを減らすような工夫をすることは非常に重要です。
ここではそのヒントについてお教えします。
1つ目は「有識者からのサポートを受けること」です。
初めての仕事ほど、有識者のサポートが必要な場面はありません。
サポートがあるだけ仕事が何倍もスムーズに進むことは珍しくありません。
有識者を探すには「いかに広い人脈を持っているか」が非常に重要で、
- 社内のベテラン社員に聞く
- 客先のエンジニアにアドバイスをもらう
- 協力会社のエンジニアにアドバイスをもらう
- 有識者を中途採用する
- 部品メーカのサポートセンターなどに問い合わせる
などのように視野を広げて探せばきっと見つかるかと思います。
またアドバイスをもらう際におすすめなのは「完成度が20%進んだらいったんレビューを受ける。これを何度も繰り返して完成を目指す」というやり方です。
何度も周囲から指摘を受けることになるので最初は疲れるかもしれませんが、この方法のほうがプロジェクト全体で通して見たときに、最小限の修正作業で済むようになります。
逆に「初めての仕事にも拘わらず、最初っから完成度100%を目指す」というやり方は、後々になって膨大な修正作業が発生するリスクが高くなるので、大きな失敗に至る可能性が高いのです。
2つ目は「お客さんから過去図面・参考図面をもらうこと」です。
これは設計に限った話にはなりますが、もし設計の依頼をいただいたお客さんから過去図面や参考図面を支給してもらえそうであれば、必ずもらうようにしておいたほうがいいです。
そうすることによって、たとえ初めて取引きするお客さん、初めて設計する装置であったとしても、図面を参考にしながら一部を流用するようにすれば、失敗のリスクを大幅に下げることができます。
またこのように図面をもらうことは、実は設計を依頼したお客さん側にもメリットがあります。
すでに成功している図面を参考に設計してもらうことになるので、完成した生産設備の不具合リスクを大幅に低減することができます。
3つ目は「スケジュールに多めの余裕を持つこと」です。
初めての仕事では、その当時は100%を発揮して一生懸命やっていたとしても、有識者からしてみれば完成度が20~30%程度にしか達しておらず、大量に修正作業が必要だということはよくあります。
プロジェクトの最初にスケジュールを設定するとは思いますが、実際にプロジェクトが始まった際にはかなり前倒し目に作業するぐらいが最終的にちょうど良かったぐらいになることが多いです。
よく起こる失敗その2:変更

- プロジェクトの途中での図面変更
- 突発的な作業スケジュールの変更、納期の前倒し
- 生産設備のマイナーチェンジ、改造による構造変更
などのような「変更」が起こる場面ではよく、失敗や不具合が発生しやすくなります。
「変更」にも色んなパターンがありますが、個人的な経験でいうと、特にプロジェクト遂行中に変更が起こるパターンが最も多いと感じます。
なぜ「変更」が発生すると失敗が起こりやすいのかというと、その理由は主に3つあります。
1つ目は「新旧の情報が混在するから」です。
例えば設計において変更が発生していた場合には、それを関係者全員へもれなく展開をしなければなりません。
ですが実際のところ、一部の関係者への展開が漏れて、関係者間で認識している情報に齟齬が生じるケースはしばしばあります。
私は現在、機械設計だけではなくソフトの設計・デバッグの仕事もしているのですが、あるプロジェクトで現場に出向いてソフト導入をしたものの「あれ、なぜだか全然うまく機械が動かない・・・」ということが複数箇所ありました。
よくよく調べて見たところ実は事前に支給されている図面が最新ではなかったことがわかったということがありました。
現場の隅の方に置かれていた図面を見ると、メカ図面も電気図面もすべて変更になっていた上で、実機についている購入品はさらに別のものが取付けられていたのです。
このようなことが起こると本来の業務に取り掛かることが困難になったり、バグ混在の原因にも鳴りかねないので、設備の品質を大きく損ねる事になってしまいます。
2つ目は「変更による他への影響を見落としやすいから」です。
例えば、
- 補強するための部品を追加で取付けたが、他のユニットの動作範囲に干渉してしまっていた
- 設備を改造するにあたり既存部品を取り外してしまったことによって、既存品種の生産品質が悪化してしまった
- 生産設備のマイナーチェンジに伴い部品を追加したところ、重量増加によってモータのトルクが足りなくなってしまった
という見落としによって、変更がさらなる不具合を引き起こすことがあります。
3つ目は「周囲との連携が取れなくなるから」です。
ものづくりで、特に製造や出荷、現地据付などのフェーズでは周囲との連携が必須となります。
- 装置を組立てるために、決められた日程までに工場内スペースを空けておく必要があったり、
- 出荷をするために事前に輸送業者へ連絡して、トラックをおさえる必要があったり、
- 生産設備の改造工事やメンテナンスをするために、エンドユーザの製造部に事前に連絡してラインを止めてもらったり、
といった具合に連携をするので、「自分の都合に合わせて突然対応してもらう」ことは基本NGとなります。
ところがここに「急な変更」があると、現場は混乱してしまいます。
以前私がとある生産現場で、施工業者さんと一緒に改造工事の対応をしに行くことがありました。もちろん事前にエンドユーザの担当者とスケジュールをすり合わせたうえで訪問させてもらいました。
ところがいざ現場に着くと、製造部の方がその製造ラインでずっと作業をしており、工事ができるような状況ではありませんでした。
客先担当者に問い合わせると、改造工事の日程について社内に共有するのを忘れていたそうで「わざわざ来てもらって申し訳ないが、いったん工事自体をキャンセルとさせてくれ」と言われたことがあります。
こちらとしては、この対応をするために他の予定との調整をしたり、近隣のホテルへの宿泊の用意をしてますし、キャンセルとなれば大きな機会損失になるということで、関係者間で口論にまで発展してしまいました。
「変更」に起因する失敗への対処法
もちろんプロジェクトスタート時には計画を立ているはずではあるものの、実際にプロジェクトを進めると多かれ少なかれ「変更」は発生してしまうものです。
むしろ私の経験上でも、すべて計画通りに完結できたというプロジェクトは存在しません。
「変更が発生している時点で計画に杜撰さがあったんじゃないのか?」というのは一見すると正論ですが、しかしそれはプロジェクトの最前線で作業したことがない人の机上の空論だと私は感じます(変更の中身にもよりますが)。
特にベンチャー企業のように、その場その場の状況を的確に判断して臨機応変に対応することが求められるような環境では、むしろ「変更」ありきでプロジェクトが遂行されることは日常茶飯事です。
ですから「変更は発生するときは発生するものだ」という前提に基づき、その中で失敗を減らせるよう取り組むことが現実的です。
そのための具体的な方法として、ここでいくつかご紹介します。
1つ目は「セカンドプランを用意しておく」というものです。
たまに「どうせ変更がおこるのであれば、計画を立てる意味なんてないのでは?」という人がいますが、それは「すべてが想定通りに行く前提の計画しか立てていない」から計画の意味をなさなくなってしまうのです。
重要なのは「計画がうまくいかなかったときにどう挽回するか、どのようなプランに変更するか?」も計画しておくことです。
機械設計でいえば、失敗のリスクが高い箇所においてはセカンドプランの設計にすぐ変更できるようにするために、
- コンパチブル(別部品へ置き換え可能)な設計をしたり、
- 部品の特定の箇所に余分に穴を設計しておいたり、
ということを優秀な設計者は行っています。
また優秀な現場作業者においては、
- あらかじめ専用ジグを作っておく
- 工具や測定器具を余分に所有しておく
といったことをしています。
2つ目は「円滑な情報共有ができる環境を整えること」です。
変更があった際に関係者間で「わたしはその変更について聞いてない」「いや、事前に言ったはずだ」という問題が本当によく起こります。
これを紐解くと
- 電話や会議にて口頭で伝えたが、相手が覚えていない。または他の話と混在している
- 誰かに伝言を頼んだが、伝わっていない
- メールやFAXを送ったが、相手が見てない
ということだったりします。
特に現場作業者は、
- いつでも資料が見れる環境ではないですし、
- 安全作業のために集中力を使わなければならない状況だったり、
- 担当者がいくつものプロジェクトを同時に掛け持ちしていたり、
という状況が普通です。
さらに関係者同士が別々の会社だったりすると、連絡のやりとりがより困難になりやすいです。
ですから、
- 連絡事項は必ず文書や資料に残す形にする
- クラウドサービスを使って外部企業との連携をする工夫をする
- 関係者が、いつでも、誰でも簡単に内容を確認できるよう資料を整理しておく
といった工夫が重要です。
3つ目は「慌てずに対応する」ということです。
これは皆さんの仕事に対する意識に依存してしまうことにはなるのですが、どんなときでも冷静さを保って業務を遂行することは重要だと私は感じます。
特に不具合対策に伴う変更業務は、納期まで残り少ない日数の中で、他のタスクもこなしながら対応することが求められるので、どうしても慌ててしまうことは普通にあります。
ですが、
- スケジュールがない中で慌てて図面変更をしたり、
- 思いついた設計のアイデアを精査することなく出図してしまったり、
- 実機で問題が発生した際に、適切な原因分析をすることなく表面的な設計変更をしてしまったり、
ということによって、さらに大きな不具合、別の不具合を引き起こしてしまうパターンはよくあります。
焦りや勢いに任せて業務を進めるのではなく、最終確認は少し時間を置いたり、プロジェクト関係者ではないエンジニアにDRをしてもらうなどの工夫をすることが重要です。
よく起こる失敗その3:久しぶり

- 既存顧客から数年ぶりに設備更新の依頼を受けた
- 部署異動で久しぶりに技術職に戻ってきた
- 現場作用員から出世して事務所勤務になったものの、緊急対応のために久しぶりに現場で作業することになった
というような「久しぶり」の作業が発生した際には、失敗について注意する必要があります。
この「久しぶり」が失敗を引き起こす原因は主に3つです。
1つ目は「記憶が曖昧になっている可能性が高いから」です。
みなさんは「会社の長期休暇明けの初日の出勤日、自分がどこまで仕事を進んでいたか思い出せない」という経験はないでしょうか?
- まず何の資料を作る必要があるんだっけ?
- この仕事はいつも誰に頼んでいたっけ?
- A部とB部、どっちを先に組み立てないといけないんだっけ?
- こういう状況の場合は〇〇してはいけないのを忘れていた
というように、人の記憶は想像以上に曖昧なものです。
大手企業の一部では可能な限りマニュアル化をしているというところもありますが、とはいっても細かくものも含めて全ての作業が言語化されているわけではありません。
2つ目は「感覚が昔と同じではないから」です。
これは現場作業でよく起こるのですが、久しぶりに作業をしようと思っても、
- 昔と違い体力が衰えている
- 腰や膝に慢性的な痛みを抱えている
- 老眼で文字が見えにくくなっている
などのように、感覚の鈍りや体への支障が少なからず発生していることが多いものです。
その状態で現場作業をするとなれば、最悪は労働災害にまで発展することにもなってしまいます。
3つ目は「現場状況が昔と変わっているから」です。
例えば久しぶりに作業をすると、
- 久々にCADを開いたら、バージョンアップによって仕様がガラッと変わっていた
- 〇〇の作業をするには、xxに申請・事前連絡が必要という業務フローに変わっていた
- 資料や材料の保管場所が、以前から変わっていた
ということはよくあります。
そのような中で自分だけが慣れ親しんだやり方をやろうとすると、現場間で連携がとれないどころか逆に混乱を招いてしまうことにもなります。
「久しぶり」に起因する失敗への対処法
最近では現場での人手不足や老後資金への不安などにより、60歳以上の方が現場復帰をするようなケースが増えてきているように思えます。
今後人手不足が大幅に改善する見込みが未だ立っていないことから、久しぶり作業者の数はしばらくは一定水準を維持すると私は予想しています。
そのような中で、久しぶり作業による失敗を防ぐための方法をいくつか紹介します。
1つ目は「ポカヨケを導入する」です。
ポカヨケとは、生産現場において作業員の誤作業や誤操作などのようなうっかりミス(ポカミス)を対策するための概念や仕組みのことを言います。
ポケヨケの導入は、久しぶり作業者にとってだけではなく、初心者の方にとっても非常にメリットがあるものですから、ぜひ積極的に導入したいところです。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
2つ目は「ある程度マニュアルを整備しておく」です。
マニュアルを作ったとて、作業者はそれで完璧に作業ができるというケースは少ないですが、それでも
- まったくマニュアルがない
- 常に誰かに聞きながらじゃないと作業が進められない
という状況に比べれば幾分マシです。
マニュアル作成は曖昧すぎると理解が難しい一方、細かく書きすぎると誰も読まないという難しさがあるのですが、作業の属人化を解消するためにも少しずつ進めておきたいところです。
またマニュアル作成後も現場の状況に合わせて更新することは忘れないようにしましょう。
私の知る限りですと、マニュアルの内容が古いまま放置されていて実質使い物になっていないということが多いのですが、定期的に見直しをしておきたいものです。
3つ目は「自分の能力を過信しないこと」です。
久しぶりの作業は「その人が過去に成功を体験してしまっている」という性質上、どうしても
- これぐらい簡単だよー
- 自分なら全然できる
と過信してしまいがちです。
ですが、現場の状況・ルールは以前と同じとは限らないですし、体の衰えも進んできています。
そのため「過去に実績がある」とはいえ、特に作業開始してまもなくは慎重に行うようにしたり、研修・トレーニングを受けるようにしておくことが重要です。