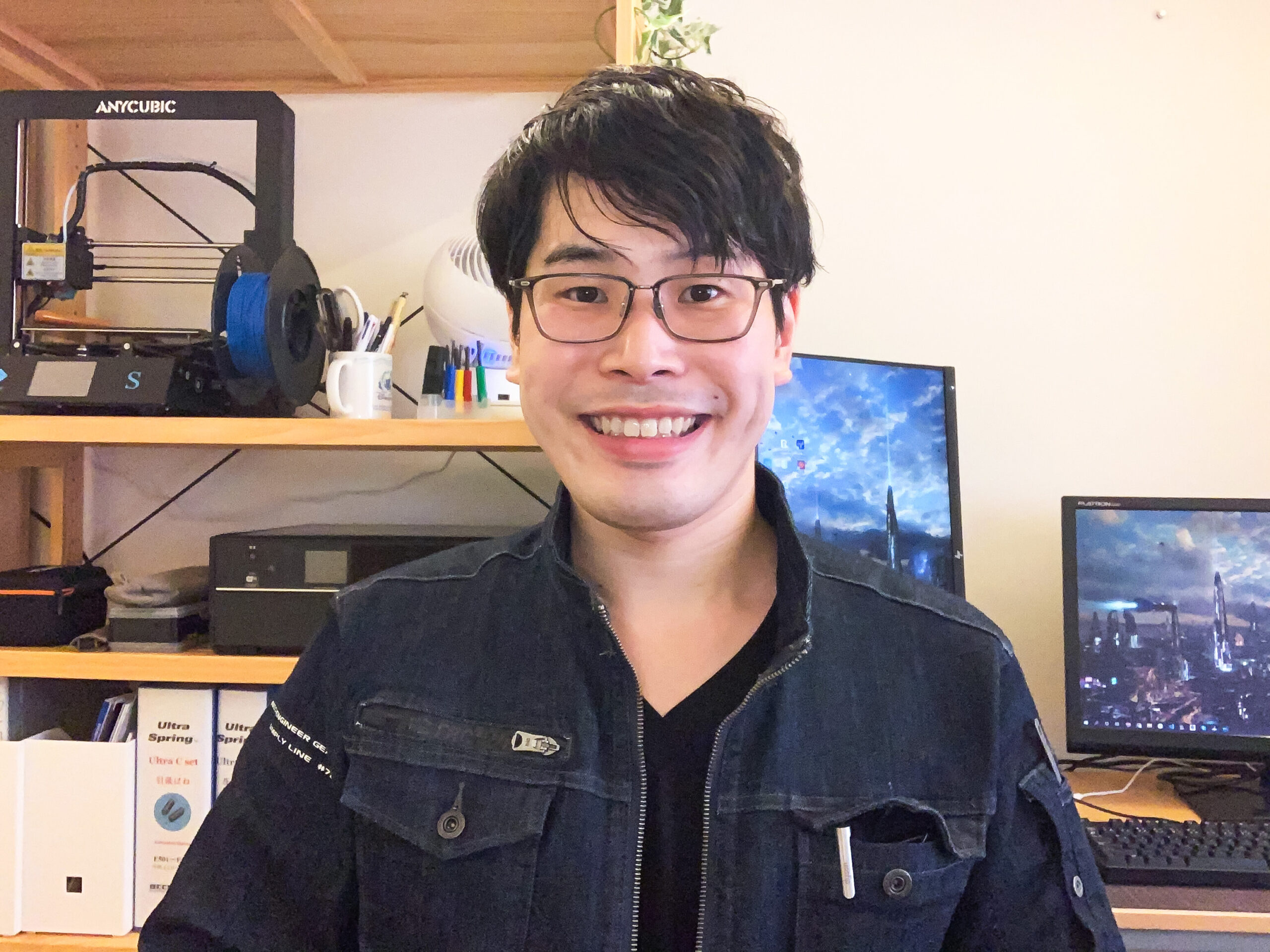こんにちは、りびぃです。
普段は生産設備の設計をしている現役のエンジニアです。
生産設備を構成する際に欠かせない要素のひとつがセンサですが、その中でも特に使用頻度が高いもののひとつが「近接センサ」です。
この近接センサは、
- 一般的な生産設備
- 食品工場の搬送ライン
- 自動車工場の組立工程
- 電子部品の検査装置
などなど幅広い分野で導入されている部品です。
特に近年は、人手不足解消、現場の生産性向上が求められる傾向が強まっており、
- ○○を簡単に検知できるよう、ここにもセンサを追加してほしい!
- 機械の状況が見える化されるようになっていてほしい!
という要求が増えてきているように思えます。
実際私自身、現役で設計業務をしていても「なんかやたらとセンサを付ける箇所が増えた気がするなー」という印象を受けており、人手不足の中で生産性を高めたいというトレンドがあるんじゃないかと考えます。
そのため生産設備・産業機械の設計者であれば、近接センサの特徴や種類をしっかり理解し、うまく設計業務で活用できるようマスタしておきたいですよね。
そこで今回の記事では、近接センサの種類や特徴について詳しく解説するとともに、それぞれのセンサの選定ポイントについてもご紹介します。
初心者の方にもわかりやすい内容を心がけておりますので、ぜひ最後までお読みいただき、生産設備の設計に役立てていただければと思います。
近接センサとは
近接センサとは、対象物に物理的に触れることなく、非接触で物体の有無や位置を検出することができるセンサの一種です。
近接センサの種類ごとに具体的な動作原理は異なりますが、ざっくり「電磁的な原理を使う非接触のセンサ」という認識でいればOKです。
非接触であるため、接触式センサで問題になるような「通常使用におけるセンサ自体の摩耗・損傷」「ワーク接触時のワークの損傷」といった懸念がないことが最大のメリットです。
同じように非接触で物体を検出できるセンサとして「光電センサ」があり、JISでは光電センサ等も含めて「近接センサ」と記述されていますが、一般的にエンジニアの間では、近接センサと光電センサは別物として認識されています。
近接センサの種類と特徴
誘導型
![]()
誘導型の近接センサは、金属を検出することができるセンサです。
読者の方の中には「近接センサといえば、金属に反応するセンサ」という認識を持たれている方もいると思いますが、単に「近接センサ」といえばこのタイプを指すことも多いです。
誘導型の近接センサの動作原理は、まずセンサ本体内で高周波の磁界を発振させます。
すると、近くにある金属材料内で渦電流が発生します。
この渦電流によってできた電磁界をセンサが検知することで、物体が近くにあることを判定できるのです。
ただし「金属を検出できる」ものの、実際には金属の種類によって感度が変わります。
例えば一般的な近接センサでは、アルミや銅、ステンレスなどの金属ですと鉄よりも検出感度が低下する(検出距離が短くなる)傾向があります。
そのため近接センサを選定する際には、検出対象物の特性を把握したうえで、適切な近接センサのシリーズを選定する必要があります。
メリット
メリットの1つ目は「耐環境性に優れている」という点です。
近接センサは、センサ自体が密閉されており、防塵性や防水性が高い構造をしています。
そのため、粉塵や油、水が飛散するような過酷な環境、高温・低温環境でも安定して動作することができます。
その上で非接触で対象物を検出できるセンサであるため、センサ本体が故障することがほとんどありません(故障するときは「センサ配線の損傷」であることが多いです)。
メリットの2つ目は「汚れ・埃等に強い」という点です。
例えば光の遮光によって対象物を検知する光電センサでは、センサの投光面および受光面に汚れ・埃があると、センサの誤検知・動作不良が発生してしまいます。
ですが光電センサの場合は電磁的な原理によって検知をするので、このような汚れ・埃の影響を受けにくいのです。
そのため、余分にセンサカバーなどを取り付ける必要はありません。
デメリット
デメリットの1つ目は「検出対象が金属に限定されてしまう」という点でしょう。
基本的に金属以外の樹脂やガラスなどは、絶縁性が高く電流をほとんど流さないという特性があるため、電磁界の影響を受けません。
電磁界の影響を受けないので、センサの信号回路に変化が生じず、結果センサが検出できないのです。
もし金属以外の検出対象ではあるものの、どうしても近接センサを導入したい場合には「ドグ」が導入されます。
ドグとは、ワークを直接検知できない場合に、その替わりとして検知をさせる金属の部品の総称をいいます。
例えばプラスチック製のワークを乗せているパレットやジグにドグを取付け、そのドグを近接センサで検知するようにすれば、間接的にワークを検出する事が可能です。
ただしうまく工夫をすることでこの性質を逆に利用し、「数ある検出対象の中から金属のみを検出する」という使い方をすることができます。
2つ目は「検出距離が比較的短い」という点です。
一般的な近接センサは、検出距離がたったの数ミリオーダです。
ですから近接センサが設置された実際の装置を見ると、近接センサと検出対象がかなりギリギリです。
そのため、検出対象が近接センサに接近する際の位置にばらつきがあったり、ドグやセンサブラケットの剛性不足により振動やたわみが発生する場合には、
- 検出距離から外れてしまい、うまく検知ができなくなる
- 検出対象がセンサ本体に干渉してしまう
などの不具合を生じる場合があります。
型式によっては若干検出距離が大きいものもありますが、その分センサ本体が大きくなり、スペースが圧迫されてしまいます。
3つ目は「検出精度にクセがある」という点です。
近接センサに対して検出対象物を近づけて検知させる際に、どのように近づけるかによって検知の可否が変わったり、ばらついたりします。
一般的には、
- 検出対象物をセンサに対して軸方向に近づけた場合に比べて、平行方向に近づけた場合の方が検出しにくくなる
- 検出対象物を平行方向に近づける場合において、センサまでの距離が遠くなるほど、検知する場所がばらつく(繰返し精度が悪化する)
という特徴があります。
そのため、センサの検出位置を高精度に行うことが必要な装置においては不向きな場合があります。
なお使用環境温度によっても、検出精度の特性が変化をする点にも注意が必要です。
静電容量型
![]()
静電容量型の近接センサは、金属だけでなく非金属の物体も検出できる特性を持つ非接触型センサです。
その動作原理は、センサの検出面と対象物の間に形成される「静電容量の変化」を利用するものです。
対象物がセンサに近づくと、その物体の材質や形状に応じて静電容量が変化し、その変化をセンサが感知することで物体の有無や位置を検出します。
メリット
静電容量型の近接センサの最大メリットは「検出対象の材質・形状が限定されない」という点です。
金属以外の材質も検知可能という事で、樹脂やプラスチック、紙はもちろんのこと、ガラスなどの透明体も検知が可能です。
また薄いフィルムや小さな粒子・粉体のような形状のワークでも、検知することが可能です。
さらには水や油などの液体も検知することが可能であり、
- タンクの残量確認
- ホッパーへの投入、排出部の流出確認
- レベル検出
なども可能です。
そのため化学プラントや食品工場などでの液体タンクや粉体を扱う工程などで活用されています。
デメリット
デメリットの1つ目は「検出距離がそこまで長くない」という点です。
先述の誘導型に比べれば検出距離は長いですが、それでもせいぜい数十mmオーダが限度です。
また静電容量型は「検出対象の材質・形状が限定されない」とはいえ、その材質や形状によってセンサの検出距離や動作が変わることがあります。
特に対象物が絶縁体の場合ですと、検知がしにくい傾向にあります。
ですから、検出したい対象物の特性を踏まえて選定をしたり、事前に実際のワークを使って検知ができるかの検証をすることが重要となります。
2つ目は「センサへの汚れ等に弱い」という点です。
静電容量型は、よく言えば「なんでも検知が可能」ではありますが、悪く言えば「なんでも検知してしまう」という特徴があります。
そのため、仮に近接センサへワークなどによる粉塵や、設備清掃時に水や洗剤などがかかってしまうと、それによって近接センサによる誤検知というトラブルに発展しかねません。
ですから汚れ等への対策をするために、
- センサの配置を十分に検討する
- カバーの取り付けを検討する
- 静電容量の感度調整をしっかりおこなう
などの対応が必要になります。
磁気型
![]()
磁気型近接センサは、磁場を利用して物体を検出するセンサで、金属や磁性体を対象とする用途に特化しています。
磁気型の中にもいくつか種類が分かれていますが、基本的にこのセンサには、磁気によって反応をするスイッチなどが組み込まれており、検出対象である金属や磁性体によってスイッチがオンするという仕組みになっています。
例えば、
- 設備の安全扉の開閉確認用のセンサとして使用したり、
- エアシリンダのロッド位置を検知するために使用したり、
というようにしてよく活用されます。
メリット
メリットの1つ目は「検出対象である磁石を大きくするだけで検出距離を長くできる」という点です。
他の近接センサは、検出距離を長くしようとするとどうしてもセンサ本体を大きくせざるを得ないのですが、この磁気型は検出対象側で対策が可能です。
ですから、センサが比較的小型で済むという印象があります。
2つ目は「検出対象物をかなり限定できる」という点です。
磁気型は基本的にマグネット等にしか反応しませんが、機械を構成する部品でマグネットを使う頻度はほとんどありません。
ですから誤検知のリスクが非常に少ないです。
デメリット
デメリットですが「検出対象が磁性体ではないと使用できない」という点があげられます。
これはメリットの裏返しにもなってしまいますが、
例えばシリンダロッドの位置検出のために磁気型を使用するにしても、そもそもシリンダにセンサ用マグネットが搭載されているタイプでないと検知をすることができません。
また、一般的にはそこまで検出距離が長いわけではないという点も注意が必要です。
選定のポイント
ここでは近接センサの種類以外の、選定のポイントについて解説をしていきます。
シールドについて
シールドとはセンサの検出面周囲に取り付ける、金属製のガードのようなもののことを言います。
このシールドを取り付けることで、センサから発生する磁界や電界の拡散を制限することができます。
図をご覧になるとよくわかりますが、シールドがない場合は磁界や電界が広く拡散してしまうため、想定外のものを誤検知してしまうなどの不具合のリスクが発生します。
![]()
特に近接センサ同士を近くに設置している場合、センサが発する磁界や電界が干渉しあうことによる誤検知や動作不安定も考えられます。
そのためシールドをつけて、磁界や電界の拡散を制限することによって、この不具合発生のリスクを低減する効果を発揮できます。
ノーマルオープン・ノーマルクローズについて
近接センサには、一般的に「ノーマルオープン(NO)」と「ノーマルクローズ(NC)」の2種類の接点動作のタイプがあります。
これはセンサの出力信号の動作方式を指しており、どのような条件で出力がオン(導通)またはオフ(非導通)になるかを示しています。
ノーマルオープンでは「ノーマル(検出物が特にない状態)においてオープン(接点が開いている)」という事なので、
- 対象物を検知していないときはセンサOFF
- 対象物を検知したときはセンサON
という挙動になります。
このタイプの近接センサは「ワークの在荷確認」「搬送機構のオーバーラン検出」などでよく使われています。
一方でノーマルクローズでは「ノーマル(検出物が特にない状態)においてクローズ(接点が閉じている)」という事なので、
- 対象物を検知していないときはセンサON
- 対象物を検知したときはセンサOFF
という挙動になります。
こちらのタイプは主に「安全用途」としてセンサを使う際に採用され「ONしている=異常が発生している」というように使用することが多いです。
このようにすることで、例えばセンサが断線・破損してしまった際に「異常発生」の信号が立つことになりますので、安全に装置を停止させることができます。
なお、このノーマルオープン・ノーマルクローズについては、近接センサの型番で決まっているものであり、近接センサの設定等では変更することができませんので、型番選定では間違えないよう注意しましょう。